
| 第4回近畿SST経験交流ワークショップ・滋賀のご報告 |
|
標記ワークショップは、東京、愛知、岡山など近畿圏外からの参加者も含め160余名の参加で、大変好評のうちに無事終了いたしました。 |
|
「第4回近畿SST経験交流ワークショップin滋賀」に参加して 2007年2月18日 ピアザ淡海(おうみ) 滋賀県立県民交流センター 記念講演 「SSTの新しい展開〜子どものSSTを中心に〜」 奈良教育大学 岩坂英巳先生 
先生がリハビリセンターで実施しておられる、注意欠陥多動障害(AD/HD)児童を中心とした軽度発達障害児童への行動療法を中心にお話しいただきました。 (滋賀県スクールカウンセラー 宮脇千恵) |
|
分科会に参加して |
|
[分科会1 入門SST] |
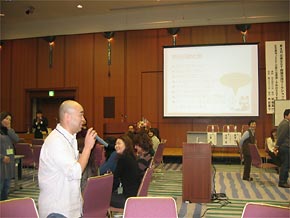 和やかに進められた第1分科会の様子 |
 |
|
[分科会2 病院のSST] 今回の近畿SST経験交流ワークショップでは、私は、「分科会2 病院のSST」に参加させていただきました。ワークショップの前日は和歌山でも強い雨だったので、当日の天気が気がかりだったのですが、結局、雨上がりの澄みきった琵琶湖の風景が印象的な滋賀行きとなりました。 (紀南こころの医療センター 杉若美智子) |
 |
 |
|
[分科会3 地域生活支援のSST] 分科会3では医療・福祉・労働等の様々な分野でSSTに取り組んでいる方、これから取り組みたいと考えている方々が知りたいこと・困っていること等、現場の苦労や苦悩を出し合い3グループにわかれて討議を深め、情報交換・知恵の交換を行いました。 (滋賀障害者職業センター 古野 素子) |
 |
 |
|
[分科会4 家族のSST] 吉田先生の発達障害の人を抱えの単家族のSSTの中では、きれいな流れで問題解決技法を入れ、理論と実践がつながった瞬間だと感じた。それも家族と本人が一緒に考えるのではなく、各個人が目標を立て実践に移していくというやり方もあると知り、臨機応変に使っていきたいと思った。 (大阪府立精神医療センター 川添 純子) |
 |
 |
|
[分科会5 SSTの良さをどう伝えるか〜協同作業としてのSST]
(同志社大学社会学部 野村裕美) |
| SST普及協会近畿支部 ニューズレターTOPへ戻る |
| ▲上へ |
Copyright (c), サイト内の無断複製および引用を禁じます。
 私がSSTに出会ったのは13年ほど前のことになる。こんなすばらしいものはないと、当時は様々なワークショップにこぞって参加したが、日々の相談業務に負われ、その後は文献を読んでは自己流で取り組む日々が続いた。今回久しぶりに参加したワークショップにて、再び自分の中のSSTへの情熱が再燃したのは言うまでもない。また自分の持っていた技法等のよきブラッシュアップの機会ともなった。
私がSSTに出会ったのは13年ほど前のことになる。こんなすばらしいものはないと、当時は様々なワークショップにこぞって参加したが、日々の相談業務に負われ、その後は文献を読んでは自己流で取り組む日々が続いた。今回久しぶりに参加したワークショップにて、再び自分の中のSSTへの情熱が再燃したのは言うまでもない。また自分の持っていた技法等のよきブラッシュアップの機会ともなった。